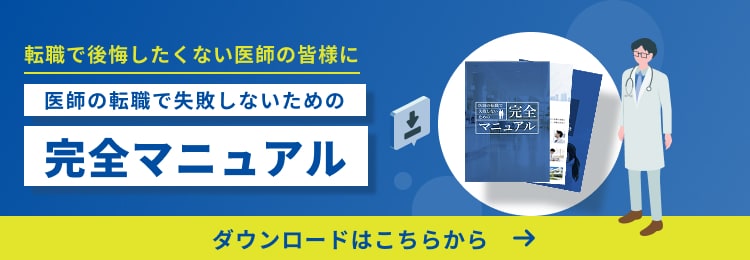こんにちは。医師転職支援会社の「メディカルプラスキャリア」です。医療現場は、日々の暮らしの中で人々の命と健康を預かる大切な場所です。日々の診療に追われ、患者さんと向き合う中で、その裏側で多くの医師が理不尽な指導や言動、あるいは複雑な人間関係のトラブルに悩まされる現実があります。特に近年、「これはハラスメントではないか」と感じる場面に直面し、精神的な負担から転職を検討される方が増えているのが現状です。
しかし、ハラスメントが疑われる状況において「すぐに辞める」ことが、必ずしも最善の解決策とは限りません。感情に任せ行動してしまうと、次の職場でも同じ問題を繰り返すことにもなりかねないからです。今回のコラムでは、医療現場におけるハラスメントの多様な実態とそれに効果的に対処するための方法、そして転職を考える前に検討すべきことについて、多角的な視点から考察していきます。
1:医療現場におけるハラスメントの多様な実態と背景
医療現場におけるハラスメントはその形態が多岐にわたり、医師の心身に深刻な影響を及ぼしています。一見指導の範疇に見える行為が、実は個人の尊厳を傷つけるパワーハラスメントであるケースは少なくありません。厚生労働省の指針にもあるように、職務上の地位や人間関係の優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境が害されるものがハラスメントに該当します。具体的なハラスメントの事例としては、以下のようなものがあげられます。
1-1. 医師も悩む:具体的なハラスメント事例
●パワーハラスメント:
威圧的な口調での叱責、他のスタッフがいる前での人格を否定するような発言、特定の医師に過度な業務量を偏らせる、不当な降格や指導放棄など。中には、患者さんや家族の前で若手医師を否定するような行為も見られます。
●セクシュアルハラスメント:
性別に基づく不適切な言動や、性的な嫌がらせ。女性医師に対しては、妊娠や出産に関する不適切な質問や発言が、マタニティハラスメントとして認識されることもあり、女性医師のキャリア形成を阻害する深刻な問題です。
●アカデミックハラスメント:
職位や指導的立場を利用した、研究や教育機会の不当な制限、意図的な業務からの排除など。
●ペイシェントハラスメント:
患者さんやその家族からの不当な要求や暴言、暴力。医療提供者側が立場上、毅然とした対応を取りにくい状況にあるため、医師が一方的に被害を受ける構造が生まれやすいという特性を持っています。
●モラルハラスメント:
医師同士の人間関係の中で生じる陰口、無視、誹謗中傷など。職場の雰囲気を悪化させ、医師の孤立を深める要因となります。
●アルコールハラスメント・ジェンダーハラスメント:
特定の環境下で顕在化し、職場環境を悪化させる行為。
これらのハラスメントが発生しやすい背景には、医療現場特有の構造があります。
続けて見ていきましょう。
1-2. 医療現場でハラスメントが発生しやすい背景
●閉鎖的な人間関係とヒエラルキー:
医療機関は閉鎖的で、師弟関係や職種間のヒエラルキーが明確なため、上下関係がハラスメントを生みやすい環境です。
●長時間労働と多忙な環境:
医師の労働時間は長く、常に多忙であり、人命を預かるという極度の緊張感がストレスを蓄積させやすい環境です。このストレスが、時に過度な指導や感情的な言動につながることがあります。
●ハラスメントへの認識不足:
過去には容認されていた「根性論」や過度な叱責が、現代ではハラスメントと見なされるケースが増えています。しかし、その認識が組織全体や個人の間でまだ浸透していない場合があり、適切な指導方法に関する知識の不足も問題の発生を助長します。
●機能不全な相談窓口:
職場に相談窓口が設置されていても、それが十分に機能していない、あるいは相談しにくいと感じる環境である場合が多く、被害者が声を上げにくい状況にあります。
結果として、多くの医師が日々の職務の中で、見えないストレスや葛藤を抱えながら業務に当たっているのが現状です。例えば、全国医師ユニオンの調査では、医師が現在の勤務先でストレスを感じる原因として「職場の人間関係」を挙げた割合も示されており、人間関係の問題が医師の働きがいや継続的な勤務に影響を与える一因となっていることがうかがえます。
2:ハラスメントに直面したときの具体的な対処法
職場でハラスメントに直面した際、最も重要なのは「一人で抱え込まず、適切な行動を取る」ことです。以下の選択肢を参考に、冷静に対処しましょう。
2-1. 信頼できる人物への相談
まず、身近で信頼できる人に状況を打ち明けることから始めましょう。同僚や先輩医師、あるいは他施設の知人など、客観的な視点からアドバイスをくれる相手が理想的です。病院によっては、コンプライアンス窓口やハラスメント相談室が設置されている場合もあります。形式的な運用に留まる可能性もありますが、まずはそうした内部窓口に相談することも一つの手です。外部の信頼できる医師や家族、友人なども含め、広く相談することで、状況を客観視し、心の負担を軽減できます。
2-2. 状況の正確な記録
ハラスメントの事実を明確にするためには、具体的な記録が不可欠です。いつ、どこで、誰が、どのような発言や行為をしたのか、その前後の状況、そして先生がどのように感じたかなどを、できるだけ詳細に記録に残しましょう。時間、場所、発言内容、目撃者の有無などを具体的に記録し、可能であれば録音データ、メールやチャットのやり取り、業務日誌などが有力な証拠となり得ます。これらの記録は、後に相談機関や法的な措置を検討する際に、非常に重要な役割を果たします。厚生労働省が定めるハラスメント対策パンフレットにもある通り、ハラスメント規制法(改正労働施策総合推進法)が施行され、企業にはパワハラ防止対策が義務付けられているため、病院側もこれらの記録を基に対応を求められる場合があります。
2-3. 内部通報制度と外部相談機関の活用
もし病院内の相談窓口が機能しない、あるいは相談しにくいと感じる場合は、外部の専門機関への相談を検討しましょう。労働基準監督署、弁護士、医師会、あるいは医師特有の労働問題に詳しい労働組合など、様々な選択肢があります。例えば、全国医師ユニオンのように医師の労働問題に強い団体は、医師特有の複雑な働き方や組織構造を理解した上で、個別のケースに対応してくれる心強い存在です。また、民間の転職エージェントなども、ハラスメントを含む職場環境に関する相談を無料で受け付けている場合があります。公的な機関としては、都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」や「総合労働相談コーナー」なども利用できます。厚生労働省のパンフレットでも、このような外部機関への相談が推奨されています。
3:安易な「転職」の前に立ち止まって考えるべきこと
ハラスメントによる強いストレス下では、「この職場から一刻も早く逃れたい」という気持ちに駆られるのは当然のことです。しかし焦りや感情に任せた転職は、予期せぬリスクを伴うことがあります。新しい職場でも似たような問題が再発する可能性も考慮し、一度立ち止まって状況を整理することが賢明です。転職を考える前に、以下の点を自問自答してみましょう。
3-1. 問題の根源を特定する
本当に職場の文化や組織全体に問題があるのか、それとも特定の人物との関係性や、その人の行動に起因する問題なのかを見極めることが重要です。ハラスメントは「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」など多様な形態を持つため、その発生源を正確に把握することが、適切な解決策を見つける第一歩となります。職場全体の問題であれば、転職が有効な解決策となる可能性が高いですが、特定の人物との問題であれば、その人物との関係改善や、配置転換などの内部的な解決策も視野に入れることができます。
3-2. 環境変化による解決の可能性
現在の職場で抱えている問題は、単に環境を変えるだけで本当に解決するのでしょうか。自身の働き方やコミュニケーションスタイル、あるいは期待値と現実のギャップなども含め、客観的に自己分析を行うことで、転職が根本的な解決になるのか否かが見えてくるかもしれません。例えば、長時間労働や過重な責任感がハラスメントの温床となっている場合、それらが解消されるような職場を選ぶことが重要です。また、過去には問題視されなかった行為が、時代の変化とともにハラスメントと見なされるようになったケースも多いため、自身の認識と世間の認識にずれがないかを確認することも大切です。
3-3. 自身のキャリア観と価値観の再確認
医師としてどのような働き方を理想とし、どのような価値観を大切にしたいのかを再確認しましょう。例えば、ワークライフバランスを重視するのか、専門性を追求したいのか、教育体制が充実している環境を求めるのかなど、自身の軸を明確にすることで、転職の目的がより明確になります。ハラスメントから離れることだけが目的ではなく、将来的なキャリアビジョンに合致した職場を見つけることが、長期的な満足度につながります。
このような自己分析と状況整理を通じて、単なる「問題からの回避」ではなく、「問題解決と自身の成長」の両立を図れる可能性も生まれます。必要であれば、中立的な立場から客観的なアドバイスを提供してくれる転職エージェントなどの第三者に相談するのも有効な手段です。医療業界の現状や各病院の特性を把握しており、先生の状況に合った選択肢を提示や、時には現在の職場で改善できる点や、転職以外の解決策を提案してくれることもあります。
4:それでも転職を選ぶ際の重要なポイント
上記のような検討を経て状況の改善が見込めず、心身の健康に支障をきたすようであれば、転職は決して後ろ向きな選択ではありません。むしろ自身の心身を守り、より良いキャリアを築くための前向きな決断となり得ます。重要なのは、「次の職場では、同じ問題が起こらないようにする」という明確な意識を持って臨むことです。転職活動を進める際には、以下のポイントを特に意識しましょう。
4-1. 職場の雰囲気と人間関係の確認
面接の際に、単に診療体制や勤務時間だけでなく、職場の雰囲気や人間関係について具体的に質問することが重要です。「チーム内のコミュニケーションはどのように取られていますか?」「若手医師への指導はどのような形で行われていますか?」など、具体的な質問を投げかけることで、職場の実態を探りやすくなります。また、面接担当者の態度や言葉遣い、質問内容からも、職場の文化や人柄をある程度推し量ることができます。
4-2. 教育・評価体制への注目
医師としての成長を継続するためには、適切な教育体制と公平な評価体制が不可欠です。これらの点が明確に整備されているかを確認することで、ハラスメントが発生しにくい、風通しの良い職場環境であるかどうかの判断材料となります。例えば、定期的なフィードバックの機会があるか、評価基準が明確かなどを確認しましょう。
4-3. 事前の現場見学の実施
可能な限り、事前に職場の見学をさせてもらいましょう。実際に現場の医師やスタッフがどのようにコミュニケーションを取り、どのような雰囲気で業務を行っているのかを自身の目で確認することは、求人情報だけでは分からない職場の「空気感」を把握する上で非常に有効です。見学中に、スタッフ同士の笑顔や協力的な姿勢、活発な意見交換が見られるかなど、細かな点に注目することで、職場の人間関係の健全性を測ることができます。
4-4. 転職エージェントの活用
医師専門の転職エージェントは、非公開求人情報だけでなく、各医療機関の内部情報(職場の雰囲気、人間関係、離職率など)を豊富に持っている場合があります。先生の希望や、ハラスメントで悩んだ経験を伝えることで、よりマッチング度の高い、ハラスメントのリスクが低い職場を提案してもらえる可能性が高まります。また、面接対策や条件交渉などもサポートしてくれるため、安心して転職活動を進めることができます。
転職は、「今の問題から逃れる」ためだけではなく、「より自分らしく、充実した働き方を実現する」ための一歩であるべきです。そのためにも、情報収集と自己分析を丁寧に行い、新たな環境で最大限に力を発揮できるよう準備することが重要です。
5:まとめ/迷ったときこそ立ち止まりましょう
医師としてのキャリアは長く、その中には様々な転機や選択肢が存在します。目の前の困難な問題に直面したときこそ一度立ち止まり、冷静に状況を分析し、多角的な視点から考えることが、後悔のない判断につながります。
私たち「メディカルプラスキャリア」では、医師の皆さまが「自分らしく輝ける場所」を見つけられるよう、転職支援に留まらず今後のキャリアパスや働き方に関する幅広いご相談をお受けしています。「こんなこと相談しても良いのかな?」と迷うような段階でも構いません。どうぞお気軽にご連絡ください。先生のキャリアを全力でサポートいたします。
【メディカルプラスキャリアへの転職相談はこちらから】
・常勤での転職はこちら→https://career.medicalplus.info/full-time/
・非常勤での転職はこちら→https://career.medicalplus.info/part-time/
■参考資料:
【全国医師ユニオン】勤務医労働実態調査2022概要
【厚生労働省】職場におけるハラスメント関係指針
【厚生労働省】職場におけるハラスメント対策パンフレット
あわせて読みたいおすすめコラム
「医師の転職はどれくらい時間がかかる?」
~成功までの期間とスムーズに進めるポイント~
転職にかかるリアルなスケジュール感と、スムーズに進めるための準備を紹介。