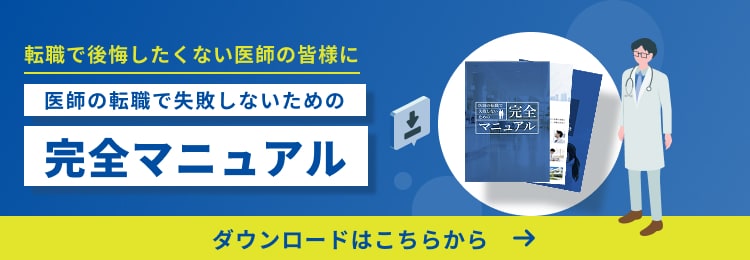こんにちは。医師転職支援会社の「メディカルプラスキャリア」です。今回は、医師が実践すべき後輩育成の5つの心得をテーマにお届けします。日々診療に追われる医療現場では、後進の育成が喫緊の課題となっています。指導する側からは「自身の業務が多忙で、後輩を指導する時間がない」という意見を多くいただく一方、後進医師側からは「教え方が人によって違う」「評価が曖昧でわかりにくい」といった悩みが聞かれます。しかし後進の育成は、単にスキルを伝えるだけにとどまりません。それは指導するご自身のマネジメント能力やリーダーシップを高め、ご自身と後進のキャリアをより豊かにするための重要な機会なのです。
この記事では厚生労働省のガイドラインを土台に、医師が実践すべき後輩育成の「5つの着手点」を具体的なステップでご紹介します 。後進の育成に悩まれている方はぜひ参考にしてください。
1:言葉をそろえる——「指導」と「育成」の線引き
後輩育成の第一歩は、組織内で「育成の目的」を明確化して共有することが重要です。育成と指導には違いがあり、指導とは「短期的なスキル伝達」を指します。一方で育成とは「中長期で自律性(判断、説明責任、多職種連携、省察など)」を高めることを指しているとお考えください。
育成の目的を共有するには、ゴールを行動で見える形にしてはっきり書くことが大切です。後輩育成の目標は、具体的に3つに絞り込み、たとえば、以下のように行動で表現するのがポイントです。
●「初診で主訴から鑑別→検査→説明までを10分で構造化できる」
●「他部署と連携し、患者さん情報の共有を1日1回以上行う」
●「手術の同意説明書を作成し、患者さんやご家族の質問に明確に答えられる」
この3つのうち、少なくとも1つは、医師に求められる「人格」「社会的役割」「基本的診療能力」といった基本理念に関わる内容を含めるようにすることをおすすめいたします 。単なる診療技術だけでなく、人としての成長につながる内容を含める事により、医師として求められる「人格」「社会的役割」「基本的診療能力」といった観点を加えることで 、知識や技術の習得にとどまらない、バランスの取れた医師の育成を目指すことができます。
2:優先順位を決める——「安全」→「共有」→「説明責任」の順
限られた時間で効率的に後輩を育成するには、優先順位が欠かせません。優先順位を整理する際には、患者さんの安全に直結する項目から着手するのが良いかと思います。
【優先順位】
●患者さんの安全:
見落としやすい症状や検査の最低限のチェックリストを紙等に明文化します 。これは医師の「基本的診療能力」に直結する部分です 。
●情報共有:
看護師や事務員への連絡事項を「1行」でまとめることを標準化します 。これは、「多職種連携」の観点と一致します 。
●説明責任:
患者さんやご家族への説明の骨子を可視化します 。これにより、「合意形成」といった「人格・社会的役割」の醸成に繋がります 。
この優先順位に沿って育成を進めることで、現場の負担を最小限に抑えながら、確実な成長を促すことができます。
3:現場の負担を減らす!「広く浅く」行う6つの観点別評価
この評価法の目的は、忙しい現場の負担を増やさずに後輩医師の成長に必要な「継続的な観察と記録」を公平に行うことです。指導側の皆さんが個々の業務に集中できるよう、評価を「深く掘り下げる」のではなく、「薄く広く」6つの重要な観点で成長を可視化します。
《 評価の6つの観点と成長のステップ 》
後輩医師の指導・育成において、以下の6つの観点から成長度合いを「初期 → 応用 → 発展」の3ステップで捉えるのが効果的ですので、ぜひ試してみてください。
| 観点 | 初期ステップ(例) | 応用ステップ(例) | 発展ステップ(例) |
|---|---|---|---|
| 1. 症例対応 | 一般的な症例を経験する | 複合的な症例に対応する | 合併症のある難症例に対応する |
| 2. 手技の習得 | 手技を見学する | 介助者として参加する | 単独で手技を実施する |
| 3. 患者さん対応 | 説明の構造化を行う | 患者さんとの合意形成を図る | クレームを予防する対応をする |
| 4. 多職種連携 | 必要な情報共有を行う | チーム内のタスク設計をする | 他職種の後輩支援を行う |
| 5. 倫理・説明責任 | 判断根拠や同意を記録する | 難易度の高い症例の相談を行う | 倫理的な葛藤を乗り越える |
| 6. 継続学習/省察 | 日々の診療から気づきを得る | 改善点を実践する | 再発防止策を提案する |
《 効果を最大化する評価コメントとフィードバック 》
評価のコメントはフィードバックがすぐに実践できるよう、以下のルールで簡潔にまとめることをおすすめいたします。
1. コメントの構造:
「良かった点 → 改善点」の順にする。
2. 事実ベース:
「頑張った」など主観ではなく、「今日の〇〇手術における手技は非常にスムーズだった(良かった点) → 術後の患者さん説明は、もう少し専門用語を減らすと良い(改善点)」のように事実に基づいて記述します。
3. 簡潔さ:
コメントは1行で完結させましょう。
翌月の成長を促すために評価の結果を踏まえ、翌月は6つの観点の中から後輩医師が1つのテーマに集中して取り組めるように絞り込みましょう。テーマを絞ることで、集中的かつ具体的な成長を促すことができます。
4:伝え方を工夫する「コーチングとフィードバック」
同じ内容を伝えるのでも、伝え方次第で後輩の成長は大きく変わります。育成効果を高めるためには、以下のポイントを意識しましょう。
4-1. コーチングで主体性を引き出す
後輩育成においては、答えを一方的に教える「指導」だけでなく、後輩自身が考え主体的に行動できる力を育む「コーチング」が有効です。コーチングの実践には、「傾聴」「質問」「承認」の3つのスキルが不可欠です。
●傾聴:
相手に心から関心を持ち、表情や話し方にも注目して話を聞きましょう。たとえ自分と価値観が違っても、まずは相手の意見をそのまま受け入れる姿勢が重要です。相手の良い部分を引き出し、目標設定を促すことができます。
●質問:
「なぜできないの?(Why)」と過去を責めるのではなく、「どのようにすればよいか?(How)」と今後の行動を考えさせる質問が有効です。はい・いいえで答えられる「クローズドクエスチョン」と、5W1Hを用いた「オープンクエスチョン」を使い分けることが大切です。
●承認:
結果だけでなく、そのプロセスも具体的に褒めるようにしましょう。一貫性のある態度で相手の長所に注目することで、後輩の自信に繋がります。
4-2. 伝わるフィードバックを意識する
フィードバックは、後輩の行動に対する評価を伝え、次の行動を促すための重要なプロセスです。後輩の性格や立場に合わせて、伝わりやすい方法を選びましょう。以下では代表的なフィードバック手法を3つご紹介します。
●サンドイッチ型:
ポジティブな内容でネガティブな内容を挟む手法です。最初に褒めて次に改善点を指摘し、最後に再び褒めることで、相手は指摘を受け入れやすくなります。
●SBI型:
Situation(状況)、Behavior(行動)、Impact(影響)の頭文字を取ったもので、客観的な事実に基づいてフィードバックを伝えます。まず具体的な状況を説明し、次にその状況での行動、そしてその行動が与えた影響を伝えることで、後輩は自身の行動を客観的に見つめ直すことができます。
●ペンドルトン型:
相手との対話を重視する手法です。まずフィードバックのテーマを確認し、その後に良かった点と改善点を相手自身に考えてもらい、今後の行動計画を立てていきます。
またフィードバックの際には、「I(アイ)メッセージ」で伝えることが重要です。「〜すべき」ではなく、「私はこう感じている」のように「私」を主語にすることで、後輩も受け入れやすくなります。伝え方によってはハラスメントと受け止められる可能性もあるため、相手の気持ちに寄り添いながら実施しましょう。
4-3. ノンテクニカルスキルの向上に取り組む
後輩育成というと、診断法や手技といった「テクニカルスキル」に焦点が当てられがちです。しかし、患者さんの安全を確保し円滑な診療を進めるためには、「ノンテクニカルスキル」の向上が欠かせません。ノンテクニカルスキルとは、コミュニケーション・リーダーシップ・マネジメント・論理的思考力といった、医療現場で必要とされる専門外のスキルを指します。医療事故を含むインシデントの多くは、このノンテクニカルスキル不足が原因で発生するとも言われています。後輩育成では、テクニカルスキルだけでなく、以下のノンテクニカルスキルを意識的に高めるよう促してみましょう。
●ヒューマンスキル:
円滑なコミュニケーションを取るためのスキルです 。
●ロジカルシンキング:
論理的に問題を分析・解決するスキルです 。
●マネジメントスキル:
業務量やストレス管理を含めた、ヒト・モノ・カネ・情報を効率的に運用するスキルです 。これら両面で後輩の成長を促すことが、医療全体の質を向上させ、チームの安全性を高めることにつながります。
5:価値観の違いを理解する——広い視野と柔軟な対応
後輩を育成する上で、世代間の価値観の違いに直面することは少なくありません。近年医師の働き方改革も進み、仕事への向き合い方ややりがいも多様化しています。しかし、大切なのは相手の価値観を変えようとすることではありません。「自分とは違う価値観がある」という前提に立ち、広い視野と柔軟性を持って接することが重要です。自身の経験を通して何を伝えられるかを考え、一方的に押し付けるのではなく、対話を通じて後輩の意見に耳を傾けましょう。このように、価値観の違いを理解し、お互いに歩み寄る姿勢を見せることは、信頼関係を築き、後輩の自律的な成長を促す基盤となります。そして、それはご自身のリーダーシップをさらに磨くことにも繋がります。
6:まとめ
後進育成の成果は、手順よりも「何から着手するか」で決まります。今回ご紹介した5つのステップ、「言葉の統一」「優先順位付け」「広く浅い評価」「伝え方の工夫」「価値観の理解」は、実践的なアプローチです。最初の一歩は小さくて構いません。育成の目的と言葉を合わせ、取り組むべき順序を決めるだけでも、現場は確実に前に進みます。もし転職を考えているなら、転職先の病院がどのような後輩育成の文化を持っているか、見学や面接時に尋ねてみるのも良いでしょう。後輩育成に力を入れている病院は、きっとご自身の成長も大切にしてくれるはずです。ぜひ、後輩育成を通して、ご自身のキャリアをさらに豊かにしてください。
私たち「メディカルプラスキャリア」では、医師の皆さまが「自分らしく輝ける場所」を見つけられるよう、転職支援に留まらず今後のキャリアや働き方に関する幅広いご相談をお受けしています。「こんなこと相談しても良いのかな?」と迷うような段階でも構いません。どうぞお気軽にご連絡ください。先生のキャリアを全力でサポートいたします。
【転職に関する無料相談はこちら】
常勤:https://career.medicalplus.info/full-time/
非常勤:https://career.medicalplus.info/part-time/